 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
「豌豆黄」は、春から夏にかけて北京でよく見かける季節のデザートです。美しい黄色をしていますが、えんどう豆の羊羹です。もともとは、一般庶民のおやつだったそうですが、後に宮廷でも食されるようになったのだそうです。
清代の西太后(慈喜皇后)が、晩年、北京の北海にある静心斎という宮殿の書斎で涼んでいた時、街の方からドラの音と共に大きな叫び声が聞こえてきたそうです。「何事か」と尋ねると、お付きの宦官が「あれは豌豆黄売りの呼び込みです」と報告したところ、その豌豆黄売りを連れてくるように命じたそうです。そして、豌豆黄売りが持ってきた豌豆黄を味わった西太后は、繊細な味わいと口解けの良さを気に入ったのだそうです。そして、その売り子を専門職人として宮中に留め、豌豆黄は庶民の食品から宮廷料理に入れられることになったのだそうです。
「豌豆黄」の作り方は、エンドウ豆の皮を取り除いてすり潰し、柔らかくなるまで煮て、そこに砂糖を加えてペースト状になるまでさらに煮詰め、クチナシで黄金色に色付けした後、冷まして、固まったら食べやすい大きさに切って出来上がりだそうです。伝統的な作り方では、ナツメの実を飾り付けるのだそうです。
宮廷小吃としての「豌豆黄」は、北京東部で採れる上質の白エンドウ豆のみを厳選して使用するそうです。そのエンドウ豆の皮を丹念に取り除き、きれいな水ですすいだ後、3度、水に浸します。その後、少しの重曹を加え、銅鍋で長時間かけてお粥状になるまで煮込みます。それを汁ごと漉し、また鍋に戻して氷砂糖を加え、木ベラでまんべんなくかき混ぜながら、さらに煮詰めます。この際、鉄製の調理器具を用いてはいけないのだそうです。鉄製の道具を使うと、エンドウが黒っぽく変色してしまうのだそうです。
エンドウ豆を煮込んでペーストを作る作業には、細心の注意が必要だそうです。火が弱すぎると生煮えになる上、水分が多すぎると冷ましても固まりません。逆に火が強すぎるて煮え過ぎると、水分が少なくなり、固まった時にひびができて、滑らかさが失われてしまいます。このようにして煮詰めたエンドウ豆ペーストを四角い浅い型に流し込み、その上にひび割れ防止のための薄い紙をのせます。完全に固まったら、指先ほどの大きさに切ります。この1つ1つにサンザシのゼリーをのせ、きれいな箱に入れて完成です。淡い黄色とサンザシの赤のコントラスが美しく、滑らかな口当たりとすっきりした甘さが特徴の上品な豌豆黄です。
イギリスのサッチャー元首相が北京を訪問した際、中国政府は宴会でこの「豌豆黄」を出してもてなし、大変喜ばれたそうです。
北京では、旧暦3月3日に豌豆黄を食べる習慣があるそうです。そのため、毎年、春になると豌豆黄が店頭に並び、春の到来を告げるのだそうです。北京では、宮廷小吃としての「豌豆黄」と、庶民のお菓子としての「豌豆黄」が売られているそうです。この2つは同じ名前ですが、材料、製造方法が異なり、当然ながら価格も天と地ほどの差があるそうです。
PR |
 |
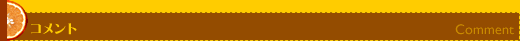 |
 |
|
|
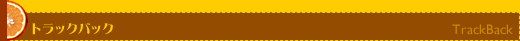 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |




